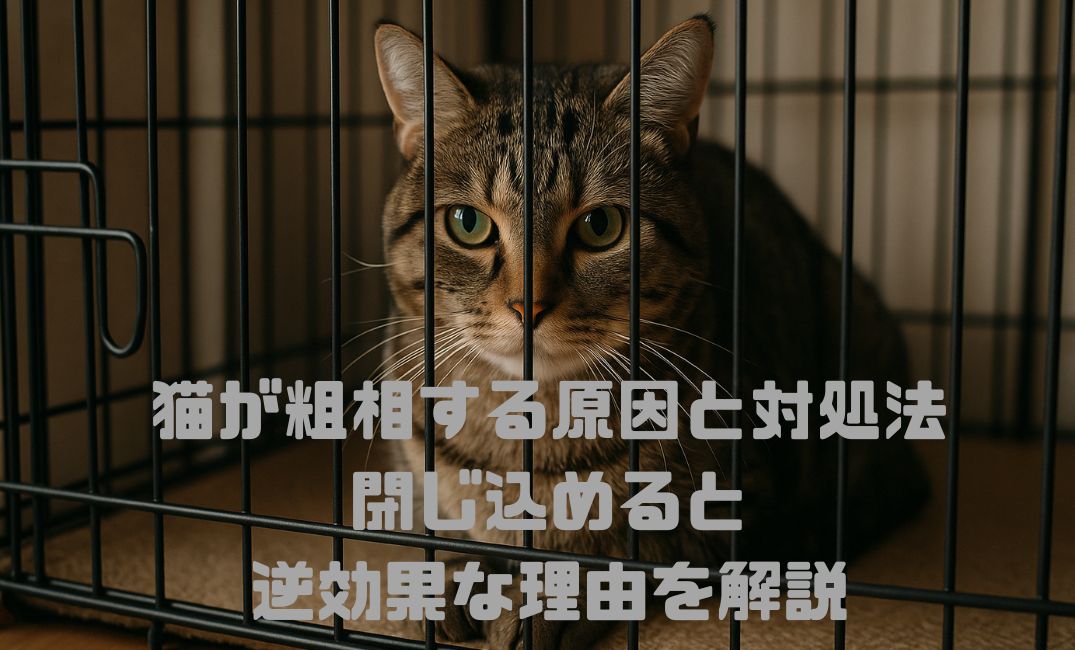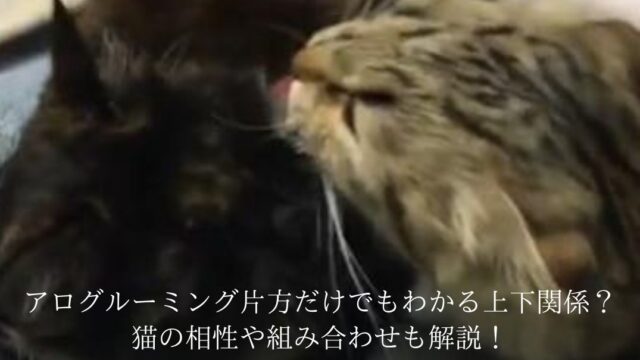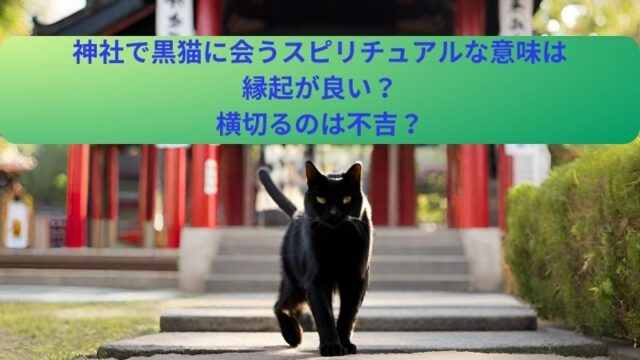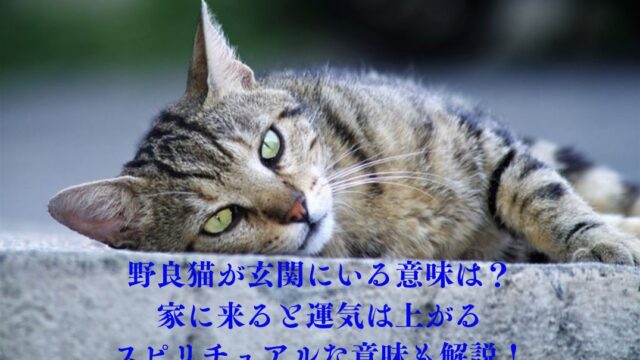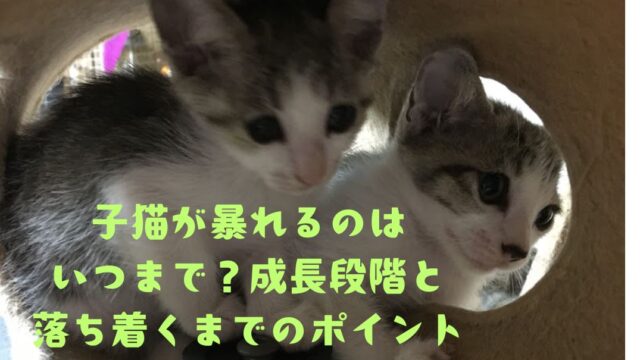猫がトイレ以外の場所で粗相をしてしまい、つい閉じ込めてしまった経験がある飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし「猫の粗相で閉じ込める」という行動は、しつけとして逆効果になる場合がほとんどです。
猫の粗相にはストレスや体調不良などのサインが隠されていることもあり、単純に叱ったり閉じ込めたりするだけでは根本的な解決にはなりません。
この記事では、猫が粗相をする理由や「閉じ込める」行為の問題点、適切なしつけの方法や注意点について詳しく解説していきます。
猫の粗相で閉じ込めるのがダメな理由とは?

猫は単独で自由に行動するのを好む動物で、「教えられて覚える」ことが得意ではありません。
さらに、猫はその場限りの記憶で行動するため、粗相を理由に閉じ込めると、その行為の因果関係を理解することができません。
理由1:猫は閉じ込められても理由がわからない
猫が粗相したあとに閉じ込められても、なぜそうされたのかを理解することは困難です。
.jpg)
一度その行為が終わると記憶には残りませんにゃ
猫は自分の行動を「悪い」と認識するわけではなく、危険を避けることを優先する生き物です。
そのため、閉じ込めても再発を防ぐことにはなりません。
理由2:猫にとって閉じ込めはストレスになる
猫は環境の変化に敏感で、急に狭い空間に閉じ込められると強いストレスを感じます。
このストレスが原因で食欲不振や膀胱炎などの体調不良を引き起こす可能性もあるため、閉じ込める行為は非常に危険です。
理由3:脱水症状を引き起こすリスク
猫はもともと水分摂取が少なく、環境の変化でさらに飲まなくなることがあります。
閉じ込めたままにしておくと、水を摂らなくなり脱水症状を起こす危険性があります。
-1.jpg)
特に夏場や子猫の場合は命にかかわることも
脱水症状は人間と同様に命にかかわることがあるため、特に暑い季節などは慎重に注意が必要です。

猫を都合で制約することは、彼らのストレスが体の維持を妨げる可能性があると理解しましょう。
理由4:飼い主への不信感・攻撃性が増す
猫を閉じ込めることで、飼い主に対して恐怖や不信感を抱き、凶暴化してしまうケースもあります。
結果として、飼い主から逃げたり隠れたりするようになり、信頼関係が崩れてしまいます。

私も以前、怖い思いをさせてしまい、それ以降中々傍に寄ってきてくれなくなってしまいました。
人間を敵とみなした猫は、日常のお世話にも支障が生じ、顔を見せれば警戒し、長時間狭い場所に隠れることが増えてしまうかもしれません。
猫の粗相で閉じ込める以外やってはダメなこと
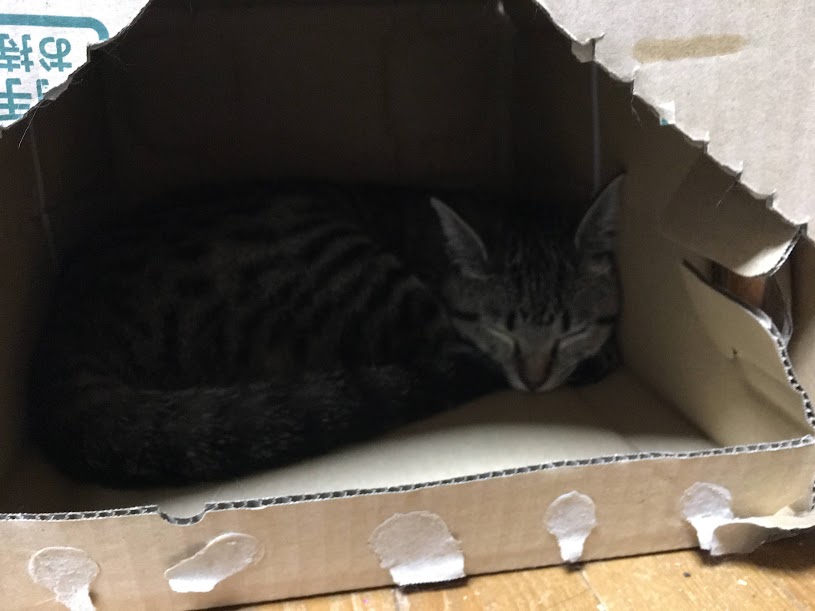
猫が粗相をした際、閉じ込める以外にも避けるべき行動があります。
大声で叱る
私も経験がありますが、猫が粗相やいたずらなどしている時につい大きな声で「だめー!」「こらー!」と叱ってしまいがちですよね。
猫は叱られても「なぜ叱られたか」を理解しません。
大声で怒鳴ると、ただ恐怖だけが残り、さらにストレスをためてしまいます。

大声で叱られることで残るのは不快で怖い記憶だけにゃ
これがストレスとなって食欲不振や遊びの減少につながります。
飼い主が叱って猫が反省しているように見えても、実際は大きな音に嫌悪感を抱いているだけです。
叩く・押さえつける
猫に対する体罰は絶対に避けるべきです。
叩いたり押さえつけたりすると、猫は防衛本能で噛みついたり引っかいたりするようになり、飼い主との関係が悪化します。

特に物で叩くと怪我の危険もあり、猫は不信感から飼い主が与えた食事を拒否してしまうかもしれません。
叩くことで猫は学ぶのではなく、逆に信頼を失いかねないため、叩く行為は絶対にやめましょう。
.jpg)
強制的に手で押さえつけられると痛くて怖く、不快感だけが残ってしまうにゃ
猫の粗相にもう限界!と悩む飼い主さんへ!こちらの記事では原因や対処法を詳しく解説しているので参考にしてください。
猫をうっかり閉じ込めてしまったときの事故に注意

意図せず猫をクローゼットや部屋に閉じ込めてしまうこともあります。
以下の点に注意しましょう。
これらの配慮を習慣化することで、猫の安全を守ることができます。
ドアを閉める前に猫が中にいないか確認する
トイレやクローゼットのドアが開いたとき、猫がスッと中に入ってしまうことってありますよね。

我が家の愛猫もよくトイレなど入って来てしまいます。
そのまま気づかないで閉じ込めてしまうと、猫が狭い空間で熱中症や脱水症状になる可能性があります。
愛猫の安全を守るために、ドアを開け閉めする際は猫がいるか確認する癖をつけましょう。
外出するときも、猫がどこかに閉じ込められていないか目で確認することを忘れずに。
玄関ドア付近に猫を近づけないようにする
玄関周辺は、猫にとってかなり危険なエリアです。
猫が玄関に近づかないようにするのが理想的で、そのためには猫のいる部屋のドアをいつも閉めておくことが良いでしょう。

誰かが出入りするときに猫が逃げ出すと、見失ったり車とぶつかったりしてしまい、最悪の場合は大変なことになります。
難しい場合は、玄関ドアの前に脱走を防ぐ柵を設置するのも一つの方法です。柵は、猫が飛び越えられない高さのものを使うのが大切です。
猫の脱走防止対策!こちらの記事では、簡単にできる防止柵を解説しているので、参考にしてください。
ベランダに出すのは避ける(転落や閉じ込めの危険)
気分転換や日向ぼっこのために、猫をベランダに出す飼い主さんがいますが、それは避けてください。
柵に登ったり虫を追いかけたりして、ベランダから落下する事故が実際に起きているのです。
猫は高い場所からの着地が得意と言われていますが、高さや地面の状態によってはそうとは限りません。
骨折や内臓の損傷、最悪の場合は致命的な結果につながる可能性もあります。
また、うっかりベランダに閉じ込めてしまって、熱中症や脱水症状になることもあるので、窓を開け閉めするときは猫が居るか確認することを忘れないでください。
猫が布団や絨毯に粗相したときの対処法

猫の尿は強い臭いが残りやすく、布団やカーペットにされると大変です。
重曹やクエン酸を使って掃除することで臭いを軽減できます。
- 布団には重曹+クエン酸でつけ置き洗い
- 絨毯はスチームクリーナーや熱湯拭き取りで対応
消臭剤を使うよりも、尿の成分を中和させる方法が効果的です。
対処法:布団に粗相された場合
猫の尿は強い匂いがあり、洗濯だけでは完全に取り除けないことがあります。
同じ場所にされることもあるため、できるだけ匂いを残さないように心がけましょう。
匂いを根本的に取り除くには、重曹やクエン酸を併用しながら、洗濯すると効果があります。
- 猫が粗相した場所に重曹を撒いて、40度前後のお湯でつけ置き
- しばらく置いた後もみ洗い
- 水で薄めたクエン酸を霧吹きなどで吹きかける
- ぬるま湯につけて押し洗い
クエン酸は添加物がなく、穏やかな酸性度なので安心して使用でき、素材に対する影響も少ないのが魅力です。
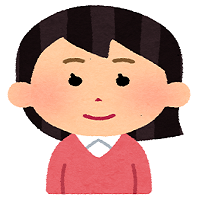
羽毛ふとんに猫が粗相をした際、臭いを取り除く方法としても効果的となっています。
猫の尿はアルカリ性なので、クエン酸の酸性で中和させると消臭効果があります。
重曹やクエン酸は100円ショップでも手に入るので、手軽に試してみることができますね♪
対処法:絨毯に粗相された場合
絨毯など洗濯できないものに愛猫がおもらしをした場合、熱湯を少量ずつかけながら拭き取る手順を繰り返すことで、ある程度ニオイを軽減できます。
水蒸気を使うスチームクリーナーを持っている場合は、より強力な除去効果が期待できますので、ぜひ活用してみてください!
猫のしつけはどうすればよい?

猫にしつけをする際は、怒るのではなく「現行犯で対応」「叱る言葉を統一」「行動を制限する」などの方法をとりましょう。
猫は時間が経ってからの叱責を理解できないため、即時対応が鉄則です。
しつけ方ポイント:現行犯で対応
猫を現行犯で叱ることができなければ、その行為は意味がありません。
猫は人間の3歳程度の知能を持っています。
学習を促進させるためには、行動と感情を結びつけることが鍵となるでしょう。

時間が経ったり、場所が変わると、なぜ叱られたのか理解できないにゃ。
また、くどくどと叱るよりも、簡潔な言葉で叱る方が猫には理解しやすいのです。
しつけ方ポイント:叱る言葉を統一
猫に注意するときは、声のトーンやセリフを統一しましょう。
例えば、「ダメ」や「いけない」を使い分けると、猫が混乱してしまいます。
猫は特定の言葉よりも音のトーンを重視します。
注意するときは優しく一貫性をもって、猫が理解しやすい環境を作りましょう。
しつけ方ポイント:行動を制限する
猫がいたずらをしてからしばらく時間が経過した場合は、黙って猫を離しましょう。
など、さまざまな対策が考えられます。
ただし、現行犯でない限り、猫を叱っても効果はありません。
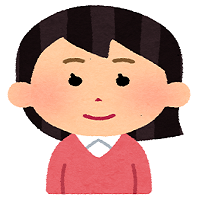
猫の行動を制限する対策を繰り返し行い、徐々に覚えさせていくのが効果的です。
飼い主が大声で注意すると、猫は誤解して「遊んでくれるのか」と思うことがあります。
このような仕組みを確立することで、猫は自然にその行動をやめるようになるでしょう。
しつけの難しさと始める時期

猫のしつけは犬と違い難しい面がありますが、トイレや爪とぎ、噛み癖など、最低限の習慣は身につけさせることが可能です。
生後2〜3ヶ月ごろから始めるのが理想で、日常生活を通じて少しずつルールを覚えさせるようにします。
猫のしつけはなぜ難しいのか
犬には当たり前のように行うしつけですが、なぜ猫には難しいのでしょうか。
-2.jpg)
猫は長時間一つのことに集中ができないにゃ。
“飽きっぽい”と思われることが多いのは、そのためです。
また、犬のように主人の指示に従い、学びやトレーニングを楽しめるとは限らず、猫はトレーニング好きな動物ではありません。
犬のように芸を教え込むのは難しいかもしれませんが、猫にも基本的なしつけするのは可能なのです。
基本的なしつけとは
共同生活に必要なトイレの訓練や、避けるべき行動を学ばせることも、しつけ次第です。
しつけを始める時期
トイレや爪とぎなど、日常のお世話に必要なしつけは、通常、生後2~3ヶ月くらいから始めるのが良いとされています。
家族や仲間との共同生活を通じて、社会でのマナーやルールを習得していきます。
従って、子猫を迎える際には「生後2ヶ月以降」が一般的なガイドラインとされています。
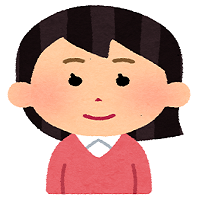
野良猫の子猫を保護した場合、親や仲間と一緒に過ごせないため、飼い主が親や仲間の代わりとなり、子猫にしつけをしていきましょう
トイレのしつけも親や仲間の模倣によって行われるため、特別な訓練は必要ありません。
生後2~3ヶ月より前に子猫を迎えた場合は、猫が不安に感じた時に飼い主がトイレに誘導すると良いでしょう。
遊びを通しての子猫は学習とは
猫を飼うときに最低限しつけたいこと

猫と一緒に生活する際には、「飼い主が猫に適応する」努力が必要です。
それに加えて、最低でも以下の3つのしつけは猫に覚えてもらうようにしましょう。
- トイレトレーニング
- 爪とぎ
- 噛み癖
トイレトレーニング
猫のトイレのしつけは通常簡単で、大抵の場合問題なく進みます。
問題が生じる場合は、
などが原因となっています。
-2.jpg)
猫にトイレトレーニングが必要ないのは、親猫の行動を見て覚えるにゃ。
粗相が起きるのは、トイレや猫の環境に何かしらの問題があるためです。
猫が粗相するのはわざとの理由は?トイレ以外でする対処法など解説!こちらでも、トイレ問題について詳しく解説しているので気になる方は参考にしてください。
爪とぎ
猫にとって爪とぎは不可欠な行動なので、それをやめさせることは難しいです。
代わりに、飼い主は爪とぎしやすい場所を提供し、爪とぎNGの場所には滑りにくいフィルムを貼ってください。
猫には「褒める」「叱る」が通じませんので、飼い主は爪とぎしやすい環境を整えるよう心がけましょう。
噛み癖
子猫は仲間たちと遊びながら、「優しく噛んで遊ぶ」ルールを身につけます。
甘噛み程度であれば問題ありませんが、強く噛んでしまう場合はしつけが必要です。
子猫の噛み癖は叱るのではなく、飼い主が遊びを中断することで改善できるでしょう。
-2.jpg)
遊んでくれなくなると子猫は「強く噛むと遊びが終わる」と理解するにゃ。
噛まれた場合は逆に手を猫の口に押し込む方法もあります。
子猫は十分な遊びが必要なので、おもちゃを使って遊ばせると手での噛みつきが減ることがあります。
猫の粗相で閉じ込めるのがダメな理由とは?のまとめ
猫の粗相に対して「閉じ込める」という対応は、しつけとして効果がないばかりか、猫との信頼関係を損なう原因になります。
粗相は猫なりのSOSであることが多く、まずはその理由を見極めて、環境改善や適切なしつけによって対応することが大切です。
猫と人間が快適に暮らすためには、理解と根気、そして優しさが必要です。